先日、大手ハウスメーカーが出していた
ファイナンシャルプランナー監修の
20~30代向けのマイホーム資金計画に関するパンフレットを
目にして改めて確信したのですが、
モデルルームにいるファイナンシャルプランナーを信じてはいけません。
そもそもお金の出所を考えれば、
ファイナンシャルプランナーが住宅メーカーに
不利な発言をするはずがないため当然といえば当然なのですが…。
パンフレットの中では、
預貯金100万円、世帯年収460万円の20代夫婦+子1人がモデルケースとなり、
頭金を貯めるより、低金利下の今住宅を建てる方が賢い選択であるとして、
頭金は親の援助とし、3,600万円のローンを組むという想定になっています。
ご夫婦の仕事内容や今後の年収UPの期待値等によって変わりますが、
基本的には、無謀極まりない判断だと思います。
終身雇用下では逃げ切れたかもしれませんが…。
今回は上記のケースを参考に、
余剰資金を十分に持たず住宅を購入することが
家計の財務状況としてどのようなことになるのか、
企業の事例と比較して考えてみたいと思います。
企業の財務健全性
企業の財務状況が健全な状態であるかを測る指標として、
貸借対照表における自己資本比率があります。
この数値は、
企業の過去の利益累計や投資家からの調達資金を
総資産で除して求められ、概ね30%超で健全とされます。
つまり、総資産の何割が自己資金で賄われているかを表す指標です。
優良企業の代表格であるオリエンタルランドの自己資本比率は
80%程度と、多少の業績不振程度では全くびくともしない
強固な財務基盤を有しています。
家計に当てはめてみると…
なぜ企業の財務健全性の話をしたかというと、
それが家計にもそのまま当てはまるからです。
ほとんど資産を持たずマイホームを購入した場合と比較するために、
まず冒頭のモデルケースで、賃借のケースを考えます。
【家計の財務諸表(賃借のケース)】
(資産)預貯金 100万円
(負債) なし
(純資産)給与等累計 100万円
上記は、給与等によって稼いだお金を
預貯金という資産の形で持っていることを意味します。
住居は賃貸であるため、ローン等の借金はゼロです。
100%預貯金で持っている是非はさて置き、
財務健全性の観点からみると、自己資本比率100%の
健全な家計とみることができます。
では親の援助を除き、
フルローンを組んだケースを見てみましょう。
【家計の財務諸表(援助以外フルローンのケース)】
(資産)預貯金 100万円
建物 1400万円
土地 1400万円
(負債) 住宅ローン 3600万円
(純資産)給与等累計 100万円
親の援助 200万円
自己資本比率をみると、300万円÷3900万円=7.7%と、
非常に脆弱な財務体質になります。
何が問題かというと、
今回のコロナ禍のように、
突然収入が減った、職を失ったなどの
想定外のリスクが顕在化したとき、
耐えられる許容量が非常に小さいということです。
余剰資金を確保しておけば、
対策を考える時間的猶予がありますが、
即、弁済不能リスクにさらされるようであれば、
資金繰りに奔走せざるを得ません。
そしてローン弁済が滞れば、
抵当権実行により保有資産は換価され、
代金で完済できなかったローンのみ手元に残ります。
コロナの影響で住宅ローンが返済できないなどの
状況に陥った家計が問題になりましたが、
多くは、当初の資金計画が甘かったはずです。
仮に冒頭のモデルケースで職を失うようなことになれば、
2~3か月足らずで家計は破綻します。
今回は政策的に救済されましたが、
そもそも借り入れ段階である程度のリスクを織り込み
ローンを組む必要があります。
結論:手元資金を確保せず家を買うのは無謀です。
十分な余剰資金が無い状況で
ローンを組んでマイホームを購入すると、
想定外のリスクが顕在化したとき、
数か月と持たない非常に脆い家計になってしまいます。
そうならないためには、
最低でも生活費の1年分、
望ましくは2年分程度の余剰資産は
確保しておくことが必要です。
そのために、
スキルを磨き労働収入を上げる、
お金の勉強を勉強して資産を運用する、
仕事以外のことでお金を稼ぐ、
出費を見直し筋肉質な家計にするなど、
まずは家を買う前にやるべきことがあります。
住宅ローンについても、
不動産業者やファイナンシャルプランナーの言いなりにならず、
どのような弁済計画を立て、
どのように毎月の弁済金額を設定するのが有利か、
税制によるメリットはどうすれば最大化できるかなど、
自分で調べたりお金の勉強をした上で、
自身の家計にとって最も有利な判断をすることが必要です。
(住宅ローン検討のポイントについては、別途投稿予定です。)
そして冒頭に記載した通り、
ファイナンシャルプランナーの話はむやみに信じてはいけません。
彼らは住宅購入を促すことが仕事であり、
あなたの家計の将来には責任を取りません。

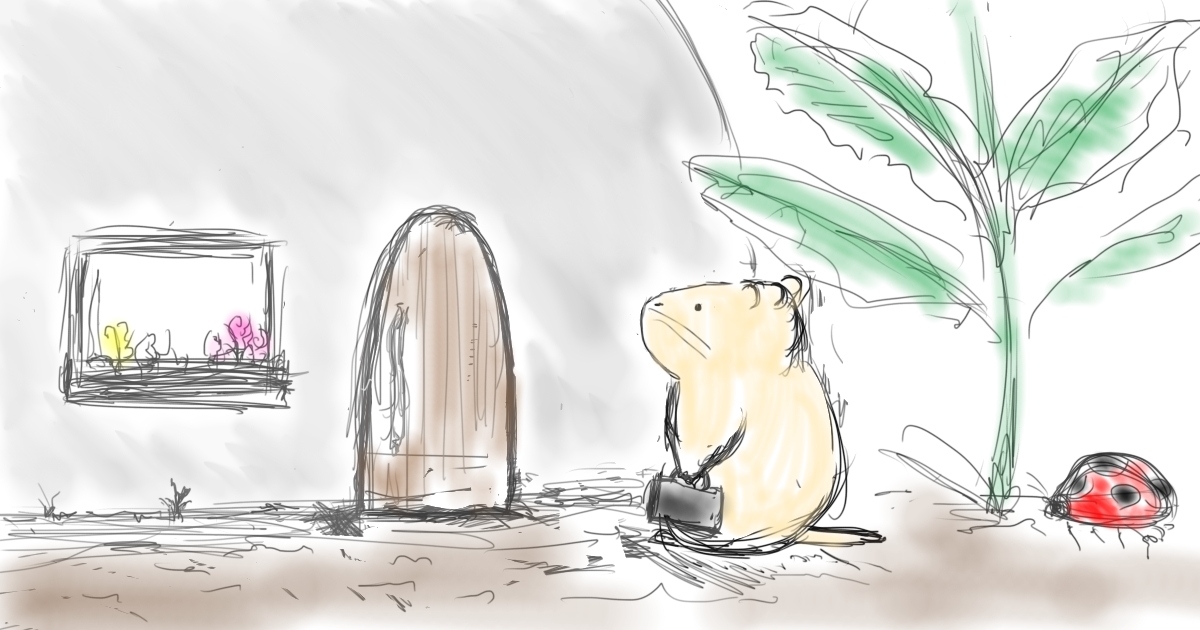


コメント